


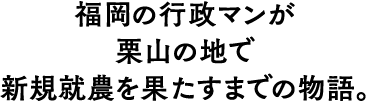
栗山町東山地区
『自然菜園らっちゃこ』
榎本 和樹さん・亜沙さん
(平成28年就農)
ご主人の前職を聞いて驚いた。
市役所勤務、場所は福岡だという。
南の都市の行政マンが、なぜ北のまちの新規就農者に?
さらに関東で生まれ育った奥様とは一体どこで出会った?
頭の中にいくつも沸き起こる「?」に戸惑いながら、
榎本和樹さんと亜沙さんを前に、真っ白な取材ノートを開いた。
榎本和樹さんは現在32歳。平成28年に新規就農を果たし、現在栗山町東山地区でメロンやトマトの栽培に取り組んでいる。小麦色の肌や筋肉質の腕を見ていると、ほんの5年前まで福岡市の職員だったことが、にわかには信じがたい。
「学生の時分から自然相手の仕事がしたかったんです。誰かに指図されその通りに動くのではなく、一から十まで自分で決めて自分で動く仕事が」
それが農業だった。場所は憧れの北海道。スケールのデカイ大地で畑を耕せたら…そう考えると胸がときめいた。だが学生には遥か彼方の夢。大学卒業後は、福岡市役所の職員として働き始めた。
「本意ではありませんでしたけれど、さすがに新卒で新規就農は無理ですから」
とはいえ、もとより指図で動く仕事が苦手な性分。モチベーションは日に日にしぼむ一方だった。逆に北海道で就農したいという夢は、日増しに大きくなった。忍耐の限界がやってきたのは勤務4年目。
「事情を話して辞表を提出し、その後すぐに北海道へと飛びました。農業の知識は皆無でしたが、勉強してからではいつになるかわからない。とにかく北海道に渡ろうと」
降り立ったのは札幌。住まいを決め、当面のバイト先も確保した。空いた時間には農業に関する情報を集めたり、就農支援機関に足を運んだりしようとも考えた。
実はこの時点で榎本さんには小学二年になる息子さんがいた。まだ幼い子どもを抱えての移住に不安はなかったのだろうか?
「なかったと言ったら嘘になります。でもどんな不安があったとしても就農したかった。息子をしっかり育て上げるためにも、絶対に農家になってやると思ってました」
その後一年ほど息子と二人で札幌暮らし。さまざまなバイトをする傍ら、北海道農業公社に足を運んだり、就農フェアに参加したりしながら、就農の機会を模索する。もちろん子育ても手抜きはしなかった。
そんな折、公社の担当から恵庭市の農業法人が研修生を募集しているという話を聞いた。スケールの大きい農場で、従業員も多く、さらに扱う作物の種類も豊富。農業の基本を学ぶにはもってこいだという。
「すぐに農場に連絡し、間もなく恵庭に移り住みました。北海道での二度目の引っ越しです」
実はこの農業法人の研修で榎本さんは、農業に関する多彩なノウハウと、将来の伴侶亜沙さんの両方を得ることになる。榎本さん、28歳の春のことである。



奥様の亜沙さんは埼玉県の出身。東京で住宅関係の営業として勤務していたが、次第に農に携わりたいという思いを抱くようになった。パソコンを開いてはインターネットで働けそうな農場を探す日々。そんな中、恵庭の親戚から地元の農場が研修生の募集をしているという話が届く。
「ホームページで働くスタッフの様子を見て楽しそうだなと感じました」
およそ3年の企業人生活を断ち切り、そのまま初めての北海道へ。不安と期待が入り混じった思いを胸に、恵庭の農場で同期8人との研修をスタートさせた。その中の一人が榎本さんだったわけだ。この農園での研修生活は2年に及んだ。当時を思い起こし榎本さんは、本当に貴重な経験を積ませていただいたという。
「ポット苗作り、トラクターやロータリーの操作、野菜の収穫、配送さらに観光農園のサポートまで。ズブの素人でしたから、毎日が新しい経験の連続でした」
研修生とはいえ労働賃金もしっかり支払われた。子どもを抱え家庭も持った榎本さんにはそれが何よりありがたかった。
さらにここでの研修生活は、当初はおぼろげだった榎本さんの営農スタイルを明確にもしてくれた。榎本さんが目指すもの、それは例えるなら、一芸に秀でた栽培技術。
「さまざまな作物を栽培するのではなく、一つ、二つの作物に絞りこみ、その栽培に関する高度な技術を習得しようと考えました。いわばこの作物作りならどこにも負けないという匠の技。2年たってようやく自身の就農の形が見えてきたわけです」
作物は技の差が歴然と現れるメロンかトマトに決めた。ただ残念ながら、それをこの農園で求めるのは、自分勝手な行動につながってしまう。榎本さんと亜沙さんは、次なる研修先、匠の技の持ち主を探して情報集めに執心することになる。

平成25年、二人は知り合いのツテを介し栗山町の土門農園の存在を知る。一粒の土にまでこだわりぬいた本格的なメロン栽培だと聞いた。おおぶりなメロンは、顧客からのオーダーで毎年完売になっているということも。
「実際にこの目で見たいと思い、二人で栗山に足を運びました。その時初めて親方にお会いしたんです」
親方とは農園の先代社長の土門氏のこと。70歳をいくつか超えた、いわゆる年配者ではあったが、体も頭脳もバリバリの現役。ベテランの一言でくくれないほどの、独自の雰囲気とオーラを放っていた。まさに榎本さんが求めた匠のイメージそのもの。さらに、その対応も卓越していた。土門氏は、初めて会った若い夫婦に、永年の苦労の末に確立した栽培方法や秘伝のノウハウを惜しげもなく教え始めたのだ。
「接ぎ木はしないこと、化学肥料も与えないこと、農薬はごくごく最小限。そして丹念に土を育てていくこと…。育成方法は極めてシンプルでしたが、だからこそ説得力があり、納得できました」
味わわせていただいたメロンの予想を遥かに超えるおいしさにも感動し、榎本さんはその場で土門さんに申し出る。夫婦で研修させてほしい、あなたの技を自分たちに伝授してほしいと。
「答えもシンプルでした。よし、面倒見てやる、それだけ(笑)。うれしさとその懐の大きさに感動して、ありがとうございます、頑張ります、と何度も伝えました」


栗山の研修生は、まず栗山の農業公社に出向き研修の希望を伝え、その後公社から紹介してもらった受け入れ先(親方)農家に研修に通う、というのが一般的だ。しかし榎本さんは違った。土門農園での研修ありきで公社に足を運ぶ。野球のドラフトで言うなら逆指名だ。
「そんなレアケースにも公社の方はしっかり対応してくれました。さらに住まいや各種の制度利用も丁寧で親切。まち全体が優しいんだなぁと感じました」
平成26年春、これで最後と息子に約束し、榎本さん一家は恵庭から栗山に移り住んだ。と同時に榎本さんと亜沙さんは土門農園の研修生として働き始める。
「うれしかったのは、親方が初年度から自分たちに畑をあてがってくれたこと。土門農園で作業したり栽培を学ぶ一方で、それをすぐに自分たちだけで実践できる、いわば実験農場を用意してくれたんです」
頭が下がった。感謝で胸が一杯になった。だからこそしっかり学び、早く独り立ちし、恩を返さねばと思った。
そこから二人は懸命に働いた。文章にも動画にもなっていない土門氏の熟練の技を、ノウハウを、作業の仕方を貪欲に吸収する日々。さらにそれを自分たちの畑で自分たちなりの知恵を加えながら再現する。初年度からメロンは実ったが、当然ながら味は親方のものには及ばない。
「それでも焦りはしませんでした。わからないこと疑問に思ったことは、親方が必ず答えてくれましたから」
少しずつ、一歩ずつ、親方の領域へ。一日がたち、季節が過ぎていくたびに、知識と技術が身についていくのがわかった。わかるほど、農は面白く、奥深いと知った。気づくと、2年の学びの期間は瞬く間に過ぎていた。


平成27年秋、就農を目前に控え二人は慌ただしく入籍を済ます。翌年1月、念願の新規就農。離農した農家の畑を借りてのスタートだった。45アールの土地にはハウスメロン、40アールの畑ではトマトやかぼちゃを栽培した。
取材に訪れたのは同年の夏。新規就農の農家としては初めての出荷を目前に控えていた。
「親方を見習い、自分の味に満足してくれる個人のお客様に販売しようと思っています。まだお客さんの数は少ないですが、目先の利益は追わず、じっくりお客様を増やしていこうと」
初年度の売上は200万円ほどの見積もり。もちろんそれで満足はできない。数年以内にその数倍の売上を実現するつもりだ。
就農を果たしても師弟の関係は続いた。親方は何かと理由をつけて、二人の畑に顔を出し土の具合やメロンの生育を見てくれた。まだまだだな、軽口をたたきながらも、あれこれアドバイスもしてくれた。二人にはそれが何よりうれしかった。
「だから今でも手が空くと土門農園に行って、作業を手伝っています。今できる恩返しはそれくらいしかないから」
本当の恩返し。それは親方の上を行くメロンを作ること、榎本さんはそう言う。その強い眼差しを見ていると、そう遠くないうちにそんな日が来るような気がしてくる。そしてふと、その極上のメロンを口にした時の親方の表情を見てみたい、と思った。
〈平成28年7月取材〉


